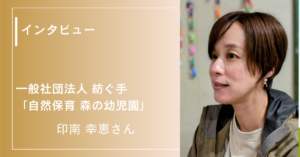怒涛の消防時代
――最年少ということですが、周りはベテランばかりだったのですか。
ベテランですし、みなさん厳しい人生を歩まれてきたからか、眉間が深く刻まれたまま固まってしまっているような、真摯に人の命を救いたいと本当に心から思っている方ばかりでした。
ガスや放射性物質といった、消防士が入れないところに特別救助隊が入ります。特別救助隊が入れないところに、化学機動中隊という化学災害の特別部隊が入ります。この部隊がサリン事件などに対応しました。化学災害の特別部隊も入れないところに特殊部隊が入るので、私は消防士として経験する仕事をだいぶ通り過ぎて特殊部隊に入ることになったというわけです。
――特殊部隊に入るとなると、どのような訓練から始めるんですか。
高校大学で学ぶような化学の基礎知識から数ヶ月で全部覚えます。特殊部隊になるということは、放射線関係の専門家になるということなんです。NBC災害(放射性物質、生物剤、危険物や毒劇物による特殊災害)に関する知識や技術を一気に勉強しました。
――1日何時間ほど勉強していたのですか。
1日何時間とかではないですね。数時間寝ている以外はずっと。パンを食べながら、お風呂入りながら、トイレの扉に貼った、覚えなくてはならないポスターを見ながら覚えるというのをひたすら。既に存在する部隊に行くのではなく、4月から発隊(隊が発足)っていうところに数ヶ月前に行って、部隊が出来た瞬間、災害があったらリアルに向かうわけです。基礎的な知識をすでに持ち合わせている人たちが集まっているのですが、訓練期間の数ヶ月でどんな災害に出ても困らないようにしなければならない。
当時の一番偉い人に、「八櫛さんだけプラスアルファの任務があります。君は部隊の中で唯一、救急救命士の資格を持っているから、部隊員の命も守らなきゃいけないんだよ」と言われました。たとえば、部隊員がガスを吸って倒れるとか、放射線を受けてがんになることがないように、部隊員の健康管理も担わないといけない。ということで、その分まで一生懸命勉強しました。
――そんなに専門的なことまでやるのですね。
そうですね。誰からの手助けも受けられないですからね。いろいろな警戒線があって、誰も入ってないところに入っていく部隊なので、医者などの専門家は来られない。ある部隊員の目が充血したとする。災害の状況に加えて、目が充血していたらこういう物質なのだろうなとか、目が充血しているけど呼吸は苦しがってないとか、そういったいろんな症状の違いで、物質を想定して。「もう少し入っていけますね」とか、「これ以上入ってはいけませんね」とか、そういう判断もしていかなくてはいけません。
――具体的には、どのように勉強をしていくのですか。
いざ勉強するとなると、アメリカにある国立労働安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH)が刊行する毒性や症状が載っている参考資料を使います。たとえば、どの程度の濃度のところに行くと、1週間以内に健康被害が出る可能性があるとか、その数字をもとに測定した濃度でその場の安全性を判断していきます。数字を消防の現場に取り入れて安全管理するというのは特殊部隊から始まっているので、当時は、一から精密な部分を作り上げていくというような感覚がありました。
――現場で印象に残った事件を教えてください。
守秘義務があるので、多くのことは話せないのですが、26歳くらいのとき、当時、致死率100%だとされていた細菌がありました。日本でも、その細菌のような見た目の物質が発見され、特殊部隊が出動しました。
無線で現場の状況を聞いたところ、最初に触った人が「手がピリッとした」と言ったという情報が入ってきました。そのとき私は、「手がピリッとしたのであれば、細菌ではなく、化学物質じゃないですか」と一言を伝えました。「化学物質の可能性もあるなら、両方対応しなきゃいけない」「防護衣は何になる、測定器はこれじゃなくてあれも必要だ」と、特殊部隊の動きがガラッと変わりました。自分が発言するまではこの活動で行くと決まっていたのが、自分の一言で動きがガラッと変わる。それも、現場に着くまでの短時間で。そのときに、自分の立ち位置っていうんですかね、自分は重要なところで重要な一言を言うような仕事をしているのだなと実感しました。
――すごい重圧というか、緊張感というか。
重圧や緊急感をそもそも感じない人間なので。いや、もしかしたら、重圧や緊張感を抱いていたのかもしれないのですが、困難を前にするとつい、わくわくしてしまうんですよね。
――特殊部隊には何年ぐらいいたのですか。
2年ほどいました。特殊部隊で階級が上がって、消防署に出て、2年程度で再び特殊部隊に戻って、また階級上がって2年ほどでまた消防署に出ていくというキャリアを歩みました。その消防署で2年ほど勤務して、30歳くらいの頃、大手町にある本庁本部に異動になりました。
本庁で訴えた「一秒でも早く」

本庁本部への赴任直後に、NBC災害の活動基準の全面改正を担当することになりました。今では日本全国で当たり前になっている「ショートピックアップ」という活動要領があります。テロやNBC災害など多数負傷者が発生した際、最小限の避難で危険度を軽減させ、最大の救助救命効果を上げるために、消防がどのような行動をすればよいかを決めたものです。
活動要領は画期的な内容で、ありえないとまで言われていました。改正にあたっては、この救助方法には絶対に効果があるとひたすら言い続けました。内閣府の危機管理室が主催するような会合で発表させてもらうなどして、救助方法を外部の人に公開して、外部の人から評価を受け、取り入れていきました。消防の仕事を外部に対して明らかにするのは、当時はあまり一般的ではありませんでしたが、私は、「一秒でも早く出して、批評してもらい、一秒でも早く直しましょう。明日災害があったらどうするのですか」と言って、外部に出しましょうと周囲に伝えていました。
実際に外部に出したら、懸念されていたような批判を受けることなどなく、建設的な意見によるコミュニケーションが取れました。専門家の先生方と、「八櫛さんがやっているこの部分には、こういう違和感があるけど、どうやって解決するの」みたいな感じで。見方によってはただ批判されているように受け取れるかもしれませんが、指摘があって私が解決策をお伝えする。違和感を指摘してくれる。その違和感はこういうふうに解決したらいいんじゃないですかねっていうことで、もうどんどん内容が精査されていくわけです。
――具体的にどのような事件を扱ったのですか。
身近でも使われるような化学物質に、別の化学物質を混ぜると、有毒な化学物質が発生してしまうのですが、昔、それを用いて命を絶つという事件が立て続けに起こりました。私が本庁に異動したのは4月でしたが、前月までに発生件数が二桁に上っていました。民間人が自宅で二つの化学物質を混ぜ合わせて化学物質を発生させて、自らを死に至らしめる。さらに、100%の方が亡くなっているという、世界でも類を見ない、とんでもない内容でした。
私が本庁に赴任してすぐ「年明けから増えてきているから、1ヶ月ぐらいで現場活動の要領を作るように」と言われ、活動要領を作成することになりました。消防隊や救急隊は人命救助のために入っていかなくてはいけないわけです。ノックダウンと言われるのですが、発生する化学物質を吸った瞬間意識を失い、に死に至るということが分かっていました。
当時、インターネットが一般の人にも普及し始めた頃だったので、調べても正しいことはあまり載っていません。発生する化学物質の危険性についても、それぞれの研究者が異なった主張をしていて、危険性・安全性の数字が違うんですよ。
どうやって正しい情報にたどり着くべきか考えて、労働災害の記録とか検証には捜査が入っているので信頼できるのではないかと思い至りました。私は現実主義なので、過去に偉い人が唱える言説だからといったことではなく、実際にどのような事件が起こったのかを調べて、その現実から、消防隊の行動を作り上げようと判断しました。
そこで、国会図書館に詰めて産業衛生学会の学会誌を読み漁ることにしました。本庁に異動になって1週間も経たないうちに「国会図書館に出勤して国会図書館で朝から晩まで学会誌を読んできます」と職場に伝えたわけです。周りから見たら特殊な人間ですよね。
学会誌をひたすらめくり、産業の中で起きた事故のことや、許容濃度について情報を収集しました。ちなみに、許容濃度とは、人が仕事をする上でこの程度の化学物質の濃度があったら、健康に被害を与える可能性があるといった濃度の基準のこと。1日8時間、週5日間、その空間にいたときに、健康に被害が出る可能性などが記されています。
調べて判明したのは、この度の事件で発生していた化学物質の濃度は、過去の労働災害で発生していた濃度よりも桁外れに高いこと。ということは、相当安全性を高くして、部隊の行動を作らなくてはならない。
そうして作成した活動要領をもとに、東京消防庁の全職員がそのルールに基づいて、現場に向かいました。関連する事件はその年だけで三桁にのぼったので、影響範囲の大きい仕事であると実感しました。そのような特殊災害に対する研究と対応は世界的にも評価され、当時、アメリカのフロリダ州で行われた国際PPEカンファランスで講演もさせてもらいました(PPEとは、感染予防のための個人防護具のこと。カンファランスとは、医療に関する症例検討会を意味する)。